Cango:真価が見過ごされている東アジアのMicroStrategy
Cango(NYSE:CANG)は、「東洋のMicroStrategy」として過小評価されている企業です。
昨今の「MicroStrategy化」トレンドが資本市場を席巻しており、ビットコインをバランスシートに組み込み、「長期的視野と資本市場ツールの活用」という物語を掲げれば高い評価を得られる潮流です。しかし、この方針は模倣が容易で、実際には多くの企業がスローガンを掲げるのみで保有状況や体系的開示、財務管理の実態はほとんど明かしません。資金調達やリスク管理、検証可能な継続的データも不透明なものが目立っています。
結果として、「物語ばかりで実際に厚みと安定性あるバランスシートを構築する企業は非常に少ない」という状況が生まれています。
では、単なる“語り手”と基盤のしっかりした企業をどのように見極めればよいでしょうか?私の考えでは、投資対象たるMicroStrategy型企業には以下三つの条件が必要です。第一に、長期保有戦略をガバナンスに組み込むこと。第二に、フォローオンオファリングや転換社債など資本市場ツールを用い、規律あるバランスシート拡大を図ること。第三に、頻繁かつ透明な財務開示を行い、安定したキャッシュフローを自社で維持すること。この三要素が相互に機能して初めて、物語主導の評価が市況の変動にも耐えうる堅固なバランスシートに転化し、相場環境の変化にも崩れない企業となります。
Cangoはこうした条件を体現する企業です。
Cangoの企業変革の軌跡
そのタイムラインを見ると、Cangoの歩みは短期間の値上がりを狙うものではなく、着実な企業変革モデルに沿っています。まず、慎重な事業売却を実施し財務基盤を再構築。経営キャパシティを安定させ、ビットコイン保有量の月次開示体制を確立した上で、ガバナンスも段階的に強化しました。
2024年11月6日、CangoはBitmain関連企業から稼働中のマイニング機器32EH/s分を現金で取得・完了。同時に、株式発行により追加で18EH/sの機器取得計画を開示し、この取引は2025年6月27日に株式決済で完了しました。これにより、Cangoは暗号資産マイニング領域へ本格的に参入。当月は363.9BTC、12月は569.9BTCを採掘し、いずれも売却はせず、MicroStrategy型のビットコイン累積戦略が始まりました。
2025年にはガバナンス改革が進展します。
5月27日、Cangoは従来の本土事業をUrsalpha Digital Limitedへ約3億5,194万ドルで売却。これは旧来型収益源を新戦略リスクから切り離す意図的な一手でした。以降、資本配分と報告体制は「ビットコインマイニング+BTC資産運用」に集中しています。
バランスシートの拡大は「現物買いの物語」ではなく、実質的な「稼働中マイニングマシン」の統合によって実現されました。6月27日には暗号資産マイニング機器の資産移転を株式決済で完了し、売却側にClass A普通株146,670,925株を発行、統合キャパシティとして18EH/sを追加。Golden TechGen Limited(GT)が約19.85%の主要株主、売却側全体が約41.38%保有。「株式によるキャパシティ拡張」取引から二つの重要なシグナルがあります。第一に、機器は米国など複数国のデータセンターに設置済みで、受け取り後すぐに稼働が可能。第二に、これらの資産をバランスシートに組み込むことで、月次開示や在庫戦略の基盤が強固となり、BTC内部生産力が持続的に供給される点です。

キャパシティ確保後、運用リズムが明確になります。7月の開示では、展開済ハッシュレートが50EH/s、月間平均稼働ハッシュレートが40.91EH/s、ビットコイン生産量が650.5BTC(前月比45%増)。期末BTC在庫は4,529.7BTC。単なる成長ではなく、継続的かつ透明な運用状況を示し、「生産量、展開状況、月平均、在庫」を並行して開示することで、投資家に明快な月次ダッシュボードを提供しています。経営陣は「売却予定なし」と明言し、HODL方針を開示に組み込んでいます。
キャパシティ・開示・ガバナンスは連携して強化されています。7月23日にはセカンダリーエクイティ取引と取締役会再編を完了、Antalpha創業者Moore Xin Jinが会長、Paul YuがCEO、Michael ZhangがCFO、Simon TangがCIOに就任し、経営陣の一元化が実現。生産・財務・エネルギーの連携体制も強化されました。BitmainやAntalphaなど業界リーダー企業との戦略提携を進め、マイニング機材調達、資産管理、エネルギー投資の柔軟性や交渉力を高めています。資産主導型の企業にとって、こうした提携は外部リスクを自社マネージできる管理体制を築く基礎となります。
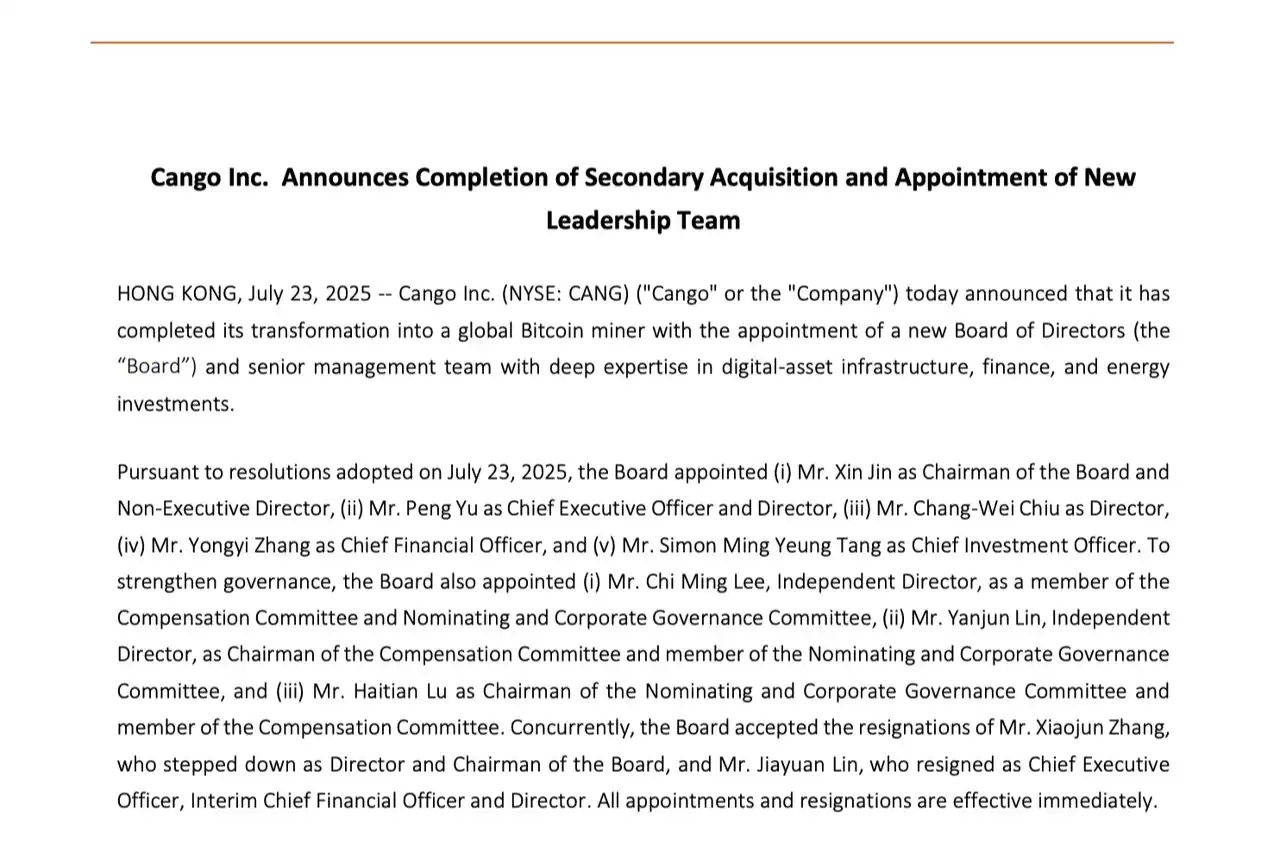
Cango、第二次買収完了と新経営陣人事発表
ミスプライシング:なぜCangoは過小評価なのか
まず、米国上場BTC保有企業の先駆者、MicroStrategyと比較します。MicroStrategyの最大の強みは資金調達力で、独自の運用キャパシティは限定的です。実際、同社の中心的な収益源を明確に把握する投資家は少数です。一方、Cangoは自社生産能力・内部マイニングエンジンを活用することで、資金調達依存度を低減し、バランスシート拡大を実現しています。
評価プレミアム指標で見れば、MicroStrategyは628,791BTC保有しmNAVは約1.68倍。市場は純ビットコイン保有額に68%のプレミアムを与えており、資金調達力とHODL持続性が評価されています。
同じ指標をCangoで見ると、2025年7月時点で開示されたBTC在庫は4,529.7BTC、当月生産量650.5BTC、展開済ハッシュレート50EH/s、平均月間稼働ハッシュレート40.91EH/s。経営陣も「売却予定なし」と示言。8月6日ビットコイン価格が約114,165ドルの際、CangoのBTC保有価値は約5億1,700万ドル。公式時価総額は約8億3,300万ドル、株価は4.70~4.73ドル。つまり、CangoのBTCカバレッジプレミアムは約1.61倍($833M/$517M)で、MicroStrategyの1.68倍とほぼ同水準。他のMicroStrategy型企業の3~10倍という高いプレミアムに比べて大幅に割安です。
しかもCangoはMicroStrategyと異なり、ハッシュレート50EH/sを自社保有。「BTC蓄積」と「生産による内部キャッシュフロー」の両方を備えた点も、割安評価の根拠となります。
日本のMetaplanetと比較すれば、Metaplanetは国内税制・投資優遇の影響を受けつつも、米国市場の流動性や機関空売りリスクに対して不利です。Cangoは米国上場、頻繁な開示、高い流動性、統合ハッシュレートという強みがあり、投資家の透明性や資本参加・期待管理面でも圧倒的優位です。
従来型マイナーと比べてもCangoの優位性が際立ちます。マイニングは収益性が高く、直近の暗号資産IPOでもマイニング企業が主役でした。

しかし従来型マイナーは「採掘→売却→拡張」の反復で、依然として価格変動リスクに晒されています。Cangoは公開HODL方針と株式を活用した拡張資本政策で「換金型」から「BTC蓄積型バランスシート」運営へ転換し、健全なフィードバックを確立しています。
数字で検証すると、Cangoの時価総額/EH/sは8億3,300万ドル÷50EH/s=1,665万ドル/EH/s、月間平均ハッシュレート基準では2,035万ドル/EH/s。北米大手ではRiotが7月末時点で35.5EH/s展開、時価総額41~42億ドル(1EH/s当たり1億600万~1億1,600万ドル)、Marathonは時価総額57~59億ドル、「energized hashrate」約54EH/sで1EH/s当たり1億600万~1億900万ドル。Cangoはこの指標で1/5~1/7程度の評価となり、明らかな割安です。
マイニング機材や効率も比較すると、Cangoの年次レポートによれば平均フリート効率は21.6J/TH、2024年第4四半期の単位生産量は17.81BTC/EH/s、Bitmain液冷モデルが約90%を占めます。電力→コイン効率では競合同等以上。地理的分散体制(米国・東アフリカ・オマーン・パラグアイ等)により、BTC単価をさらに押し下げる余地が大きく、市場低迷時も競争力を拡大できます。

Cangoの今後の展望
Cangoの本質的な評価の源泉は流行語ではなく、堅牢で持続的なバランスシートの構築力です。
「基本原則」視点では、Cangoはビットコインを戦略的な企業準備資産と位置付け、経営陣は「売却予定なし」と公開。キャパシティ・生産・在庫の月次開示を徹底し、HODL方針を市場が継続的に検証できる体制を築いています。
本質的な長期主義とは、単に長期間保有すること以上に、月次で責任ある説明を果たすことです。開示情報を見れば、価格変動だけでなく、在庫増加の安定性、キャパシティ活用体制、ガバナンスの土台が明らかです。Cangoは不確実性を運用プロセスに転換し、それを体系的な報告に変えることで、市場サイクルに耐えうる企業体質を作っています。
マイニングで勝つには「電力価格がすべて」です。長期的に多様な地域で安価・再生可能エネルギーを確保できる企業が、市場低迷時にもBTC単価を下げて競争優位を築けます。Cangoの新経営陣はマイニング、金融、エネルギー投資の専門性を結集し、「電力→キャパシティ→保有→資金調達」のクローズドループを構築しています。
Cangoの次の一手はエネルギー戦略をより深く最適化することです。北米で長期電力契約やデマンドレスポンス獲得、中東で余剰・グリーン電力活用、南米・東アフリカで低コストかつ柔軟な電源確保。ハッシュレート運用力と電力マネジメントスキルを活かし、AI企業向けHPCインフラ提供による第二の成長分野開拓も視野に入ります。ハッシュレート展開が最前線、安定したバランスシートが後方支援、その間に電力契約・運用効率・資本ツールのシナジーを重ねる仕組みです。
エネルギーとマイニングの完全統合は一気に進むものではなく、プロジェクト単位で段階的に規模を拡大し、「低電力コスト+高稼働率+再現性あるオペレーション」という企業力を着実に強化するアプローチです。ベア相場では耐性が高まり、ブル相場では素早い拡張と資金調達力アップが実現します。
Cangoは「高値買い・暗号資産追い」の物語を語っているのではなく、「自社キャパシティでBTCをバランスシートへ固定する」という本物の戦略を実践しています。自社マイニング機器によるBTCキャッシュフロー創出、徹底した開示体制、HODL方針の制度化によって、長期複利的な価値が制度化されます。
これこそ、Cangoが「本物の東洋型MicroStrategy」として果たすべきコアバリューです。
免責事項:
- 本記事はBlockBeatsより転載しており、著作権は原著作者(BlockBeats)に帰属します。再掲載に関するご要望はGate Learnチームへご連絡ください。定められた手続きに沿って対応いたします。
- 免責事項:本記事の内容・意見は著者個人の見解であり、投資助言を目的としたものではありません。
- 他言語版の翻訳はGate Learnチームが担当しています。Gateの明記がない記事の無断複製・転載・配布はご遠慮ください。
関連記事


ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

分散型台帳技術(DLT)とは何ですか?
